
ご逝去当日~翌日
1.お亡くなりになったら
病院、ご自宅などで亡くなられる場合、医師によるご臨終を告げられた後、看護師などに清拭して頂き、死亡診断書を受け取ります。
2.搬送
寝台車で病院からご遺体を移送します。深夜でもすぐに当社にご連絡ください。

3.遺体安置
ご遺体を安置し、枕飾壇に枕飾り、枕ダンゴ、ご飯を供えます。(宗教によって必要ないときもあります。)
ご家族やお身内、ご友人にご連絡します。
4.死亡届・火葬許可証
区、市役所に死亡届けを提出し火葬許可証の交付を受けます。
5.お打ち合わせ
寺院への連絡、関係者に連絡、喪主・世話役の決定。葬儀の場所や規模の決定 火葬場の予約。通夜、葬儀の日程。故人の写真のお預かり。 葬儀費用のお見積もり。お手伝いの方の役割分担。返礼品、お料理等の手配などたくさんのことを決めなければなりません。
経験豊富な日典のスタッフにご相談ください。いろいろなアドバイスでみなさんをお助けします。

お通夜前~お通夜
6.納棺
納棺とは、遺体を棺に納めることです。ご遺体を整え、旅立ちの衣装を着せて棺に納めます。
御納棺は当社スタッフが立ち会って行った方がいいでしょう。
棺の中には、故人の愛用品などを入れますが、火葬場では不燃物が禁止されていますので当社スタッフに聞いてください。
故人には遺体が傷まないようにドライアイス等を使用します。
7.お通夜
通夜とは、ご遺体を葬る前に故人にゆかりの深い人々が集まって、故人の冥福を祈り、別れを惜しむ集いです。
近年では夜通し棺を守るのは、肉親と親類などごく限られた人だけになってます。
各係員が配置につき弔問客の受付を行い、そして僧侶による読経、焼香を行います。
ご葬儀~ご葬儀後
8.ご葬儀・告別式
葬儀と告別式は別の儀式でしたが最近は区別せずに同時に行うことが多いです。
遺族親族は着席し係員は弔問客を受け付けます。僧侶による読経を行いますが読経中に遺族、近親者が焼香を行います。
葬儀と告別式を区別しない場合にはそのまま参列者の焼香になります。
9.最後のお別れ
告別式が終わると、親族による故人との最後の別れとなります。
棺のふたがあけられて、別れの対面が行われ、祭壇に供えられていた花を各人の手でご遺体の周りに飾ります。
棺のふたを閉じたら、親族や友人などの男性が棺を運び出し、霊柩車に納め出棺となります。
喪主または親族代表の挨拶を行い、霊柩車、ハイヤー、マイクロバスで火葬場に向かいます。


10.火葬
火葬場では受付で火葬許可証を提出し火葬を行います。
火葬にかかる時間は1~2時間くらいなので控室で待ちます。火葬がすみますと、一同は再びかまどの前に集まって骨あげをします。
火葬後に受付で埋葬許可証を受けます。
11.葬儀を終えて
家に帰った後、お骨・遺影・位牌は後飾り祭壇に安置します。
そして初七日の法要を兼ね、精進落としを行います。
初七日法要のあと、僧侶の方をはじめ、葬儀の手伝いなどでお世話になった人たちに、酒や料理をふるまう会食が精進落としです。
その後
12.後飾りと納骨
後飾りの祭壇に、ご遺骨、位牌、遺影写真他、小物を安置します。
一般に四十九日法要の時、塗位牌に入魂して取り替えますので、お早めに塗位牌をご準備下さい。
納骨は四十九日法要終わってから行なうことが多いようです。この時に埋葬許可証が必要になります。
13.アフターケア
葬儀後には各種手続きの書類をご用意する必要があります。
相続や税務、不動産の名義変更など相談員が対応しますので、どんなことでもご相談ください。
また仏壇選びのアドバイスや墓石のご案内などお気軽にご相談ください。


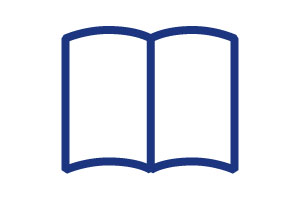 葬儀プラン
葬儀プラン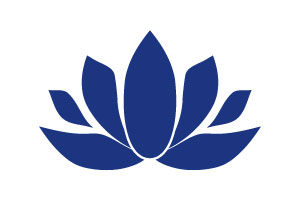 供花のご注文
供花のご注文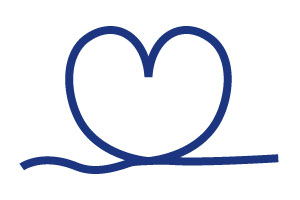 日典の想い
日典の想い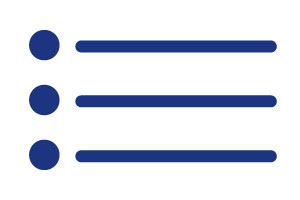 葬儀の流れ
葬儀の流れ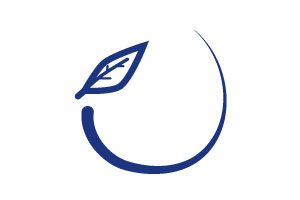 そよかぜ会員
そよかぜ会員 事例一覧
事例一覧